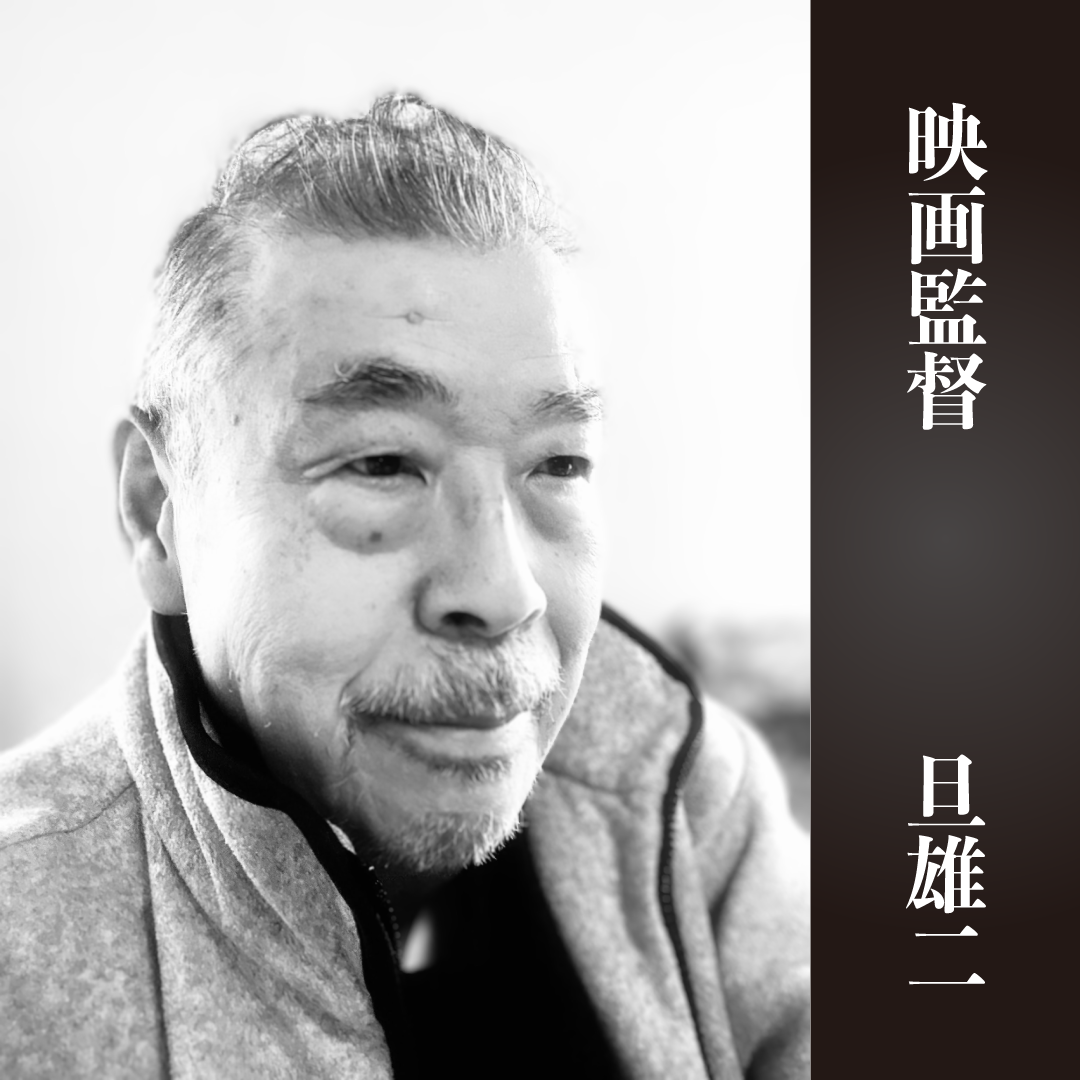
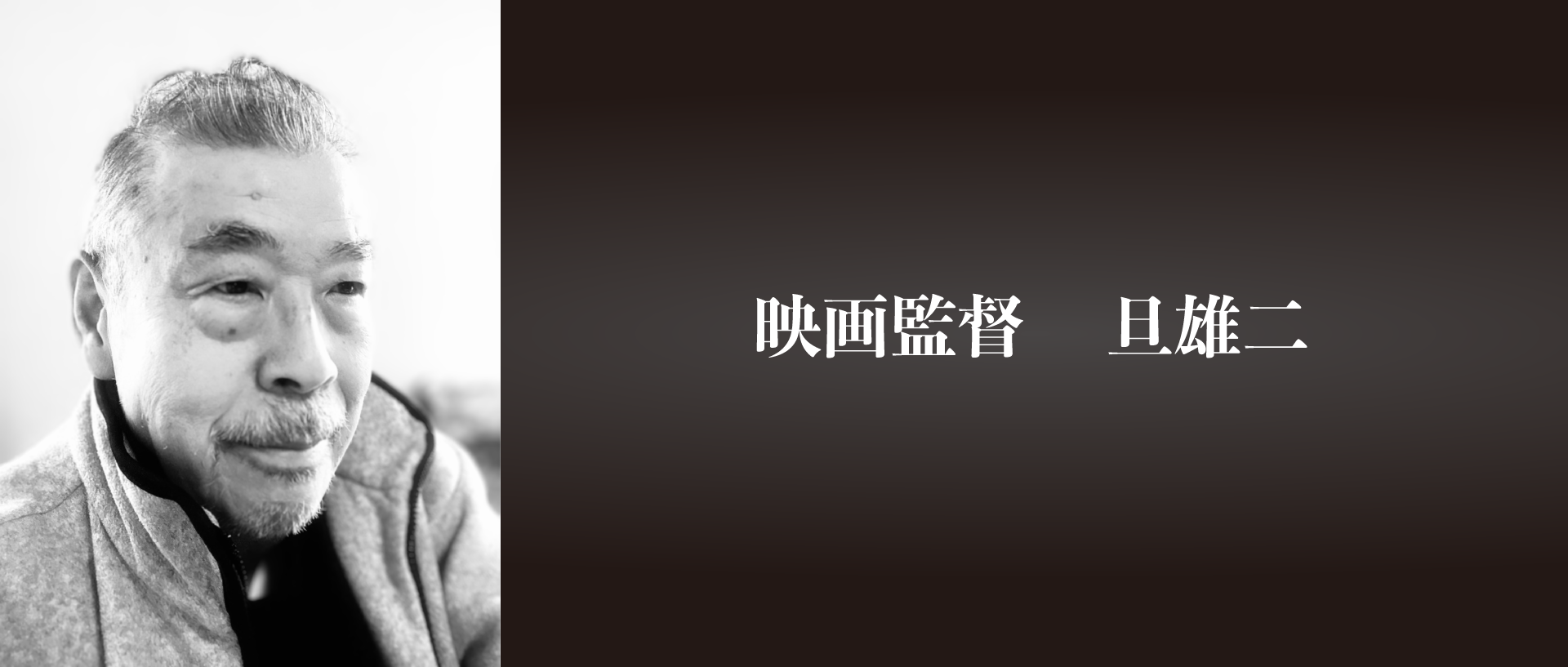
PROFILE
旦 雄二(だん ゆうじ、1952年3月24日 - )
日本の映画監督、脚本家、CMディレクター、映像クリエイター。日本映画監督協会会員。
1985『城戸賞』 日本映画製作者連盟 城戸賞選考委員会 シナリオ『助監督』にて
1994『ACC奨励賞』 全日本シーエム放送連盟 テレビCM『河合塾』デニス・ストック篇にて
1997『HVC特別賞』 通産省(現経産省)外郭団体HVC(ハイビジョン普及支援センター) ドキュメンタリー『烈 ~津軽三味線師・高橋竹山〜』にて
BIOGRAPHY
1952年(昭和27年)3月24日、大阪市阿倍野区阪南町にて、関西大学教職員(社会学部など各学部事務長を歴任、のちに、大学全体を統括する事務局長)の父・菊男(注1、2、3)と、大阪・船場(せんば)の老舗履物小売問屋『こまつ』のいとはんであった母・多惠子(旧姓=小松)(注4)とのあいだに三男として生まれる。次男が生後間もなく夭逝していたことから、名前に「二」の字がつき、次男として育てられた(戸籍上は三男)。自分が三男だと知ったのは、のちに成人してからのことであった という。
ひ弱で内気な少年であった。そのため幼稚園から小・中学と孤独で陰鬱な子供時代を過ごしたが、1967年、高校(私立桃山学院高等学校 St.Andrew's School, Osaka)入学に際して そうした自分を変えるべく 生徒自治会役員選挙にみずから立候補、その結果、トップ当選を果たし、同校はじまって以来の、一年生での生徒会長(生徒自治会執行委員長)となる。折しも時代は「激動の季節」といわれた1960年代末。左右両翼の上級生執行委員たちから熱い洗礼を受け、それまで考えたこともなかった政治や社会問題に目覚めることとなった。
その一方で、幼少のころから親に連れられて毎週のように東映チャンバラ時代劇を映画館で観つづけてきたことにより芽生えた、映画という夢のメディアへの興味・関心・憧れが、小・中・高と上に進むなかで ヌーベルバーグやアメリカン・ニュー・シネマ、ATG映画やアンダーグラウンド・シネマと出会うことによりさらに高まって、映画館に通いつめてはみずからも8ミリキャメラで映画を撮る、いわゆる映画少年となっていく。映画を一生の仕事にする志をたしかなものとした。
1971年、大学ではその映画の重要な基礎のひとつである美術を学ぶことにし、武蔵野美術大学に進学。美術全般、デザイン、舞台美術を修める。部活では映画、演劇、政治、社会活動に取り組み、没頭した。
1975年、同学卒業と同時に映画界に入る。ピンク映画および日活ロマンポルノ(外注作品)の助監督をつとめ(制作を兼任)、1978年までの4年間、山本晋也監督および渡辺護監督に師事。ほかに稲尾実(深町章)、早坂絋(難波敏夫)、中村幻児、栗原幸治(現場応援のみ)、大井由次(同)、代々木忠(同) ── 以上の監督に、応援、見習いサード、セカンド、チーフとして、助監督についた。
1978年、映画界からCM業界に移り、名門CMプロダクション、キャップ(現・ハット)に入社。1980年までの3年のあいだに、制作進行からプロダクション・マネージャー、アシスタント・プロデューサーを歴任。その一方で企画演出部にも属し、プランナーやアシスタント・ディレクターをつとめた。岩本力、里見征武、屋宜博の三ディレクターに師事。先輩社員で兄弟子の市川準から、CM企画と画コンテを学ぶ。
1980年、同社を円満退社。映画界に戻るつもりが、大手映像制作会社でCMプロダクションの東北新社から招かれたのを機に、フリーのCMプランナーとして活動をはじめる。
1981年、一年遅れでキャップを退社した元・上司、屋宜博および市川準の二人と合流し、CM企画演出事務所・BEER(ビール)を共同設立する。三人のうち誰が演出(=監督)するCMも企画はすべてかならず企画会議をひらいて全員で考える ── キャップ伝統の企画立案システムを踏襲した。(同所は1983年に市川準が脱退したのち、1986年に解散)
1981年、BEERを起ちあげたその一方で、個人としては、『富士通OASYS』テレビCM(東北新社:出演=出光元)の演出に抜擢されて、ディレクターに昇進。以後、現在にいたるまで、CMディレクターとして数百本のテレビCMを企画・演出する。
1985年、CM演出絶頂期の過密スケジュールのなかにありながらも、みずからの原点である映画への想い絶ちがたく、その映画界在籍時代を題材にして、日々の通勤満員電車のなかで立ったまま原稿用紙と格闘しつづけ書きあげたシナリオが、その年の城戸賞を受賞する栄誉に輝く。そのシナリオ『助監督』は、助監督経験者をはじめとした数多くの映画人たちから熱い支持をうけ、また、映画の道を志す若者たちのあいだでは、バイブルとまでいわれるようになった。同シナリオには複数の映画制作会社から声がかかり、順次各社に赴いて、みずから監督するために、映画化に向けての企画開発や制作準備をともに行なったが、いずれも残念ながら、実現にはいたらなかった。
1980年代の終わりごろからテレビCM以外のオファーも相次ぎ、音楽PVやアイドルもの、バラエティ、ゲーム、大型映像、PR映画、企業ビデオ、セルビデオ、ドキュメンタリーなど映像メディア全般をクロスオーバーして幅広く手がけることになり、いわゆる ハイパー・メディア・クリエイター としての活躍をみせた。
1990年代中盤から2022年春まで、東放学園専門学校の講師(CM基礎、CM研究)、同映画科(のちの東放学園映画専門学校)起ちあげプロジェクトチームメンバー、同科開設および同校開校後のトータルアドバイザー、指導教官(卒業制作)、講師(演出編集概論、CM基礎、CM研究、特別ゲスト講座プログラミングおよび運営)として、後進の指導育成につとめた。
2001年、みずからの原点である映画の世界に本格的に復帰し、自身初となる長篇劇映画の『少年』製作に着手する。監督のみならず製作総指揮やプロデューサーを兼任したその作品は、撮影に3年、さらに編集と音楽に3年の歳月をかけ、「大作インディーズ映画」ともいうべき壮大なスケールのものになった。
2007年、編集と音楽づくりが一応の区切りを迎えて2時間57分の仮編集暫定完成版の体裁になった同映画が、公益財団法人ユニジャパンの求めに応じてその仮編集版のまま同法人のオープンライブラリーにおさめられ、ちょうどそのころ来日して日本映画の作品選定を行なっていたドイツ・ニッポンコネクション映画祭やスペイン・バルセロナ・アジア映画祭のプログラミング・ディレクターたちの目にそれがとまって、両映画祭から未完成作品のまま正式招待されるという異例の厚遇を受けることとなった。それぞれの国で正式上映や特別上映が行なわれた同映画は、いずれも世界的な映画祭ゆえ国境を越えてヨーロッパ各地から集まった熱心な映画ファンたちのあいだで、たかい関心を呼び、大きな反響を巻き起こした。
2022年、仮編集版がヨーロッパでたしかな手応えを得ながらもその後 諸般の事情により長きにわたって中断を繰り返してきた同映画の編集・仕上げ作業が、劇場公開のための最終完成版アップをめざして、いよいよ本格的に再開された。
2024年末、仮編集版にはなかった4つのシーンをあらたに加え、撮影開始の1999年の時点からじつに25年の歳月を経て、ついに、総尺3時間の大作となって同映画は完成した。2000年の日本を描きつつも、いまに通じる普遍的な作品に仕上がった。
2025年、同映画は、3月29日から東京新宿の映画館 k's cinema にて公開され、予想をはるかに上回る大きな反響、熱い支持、高い評価を受けた。それに応えるべく、現在、全国拡大上映をめざしている。
注1:菊男の生家は、大阪の靭(うつぼ。現・大阪市西区靱本町)で江戸安政時代から明治、大正、昭和と代々つづいた老舗の干鰯(ほしか)問屋(注2)であったが、文学青年で小説家志望の菊男は、一人息子でありながら跡目を継ぐことを拒み、勘当されて家を出たという。その旦家(注3)をふくむ靭一帯の干鰯問屋街は、大阪の綿花栽培産業および紡績産業と連携して商都大阪の発展に寄与したが、先の大戦ですべて焼け野原となり、戦後、広大な公園に生まれかわった。
注2:干鰯(ほしか)は鰯からつくる魚肥で、有機質肥料の一種。江戸時代に日本近海で大量に獲れる鰯から脂だけを抜いて乾燥させ、綿花を栽培する畑に贅沢に撒いたのが、はじまりという。干鰯産業は江戸から明治、大正、昭和と、商都大阪の綿花栽培業および紡績産業と結びついて、隆盛をきわめた。
注3:旦家の苗字「旦」は、先祖代々の墓に刻まれているように、正式には、木偏に、旁(つくり)を「面」の下に「且」と書く。檀一雄らの「檀」に似た字だが、より複雑で画数が多い。いまではもうどこにもない古字である。江戸から明治の時代に入り、国家による苗字整備の施策をうけ、簡易な「旦」の表記にあらためたものと思われる。
注4:多惠子の実家である船場『こまつ』は、心斎橋筋に小売店舗をかまえて大層繁盛したが、先の大戦を機に没落、戦後は菓子小売問屋に転じて大阪市東住吉区南田辺に移り、その後、当主・小松鹿一の他界を機に廃業した。
FILMOGRAPHY
劇映画
1974『友よ、また逢おう』(習作短篇 8ミリ)
2025『少年』(第一回監督作品)
ドキュメンタリー
1996『寺山修司は生きている』(製作:東北新社)
1997『烈 ~津軽三味線師・高橋竹山〜』(同)
(いずれもNHK-BSおよびBS-TBSにて複次放映)
アイドル・バラエティ
1988『レモンエンジェルの あぶないビデオTV』シリーズ
(フジテレビ/創映新社/プルミエ・インターナショナル)
テレビCM
『大阪ガス』大竹しのぶ篇
『岩谷産業』浜木綿子篇
『東洋シャッター』笑福亭鶴瓶篇
『武田 タケダ』杉浦直樹篇
『ソルマック』渡辺文雄篇
『出光』山下真司篇
『NEC』三田寛子篇
『ポラロイドカメラ』イッセー尾形 番外篇
『講談社コミックス』ケーシー高峰篇
『アロナン化粧品』名古屋章+根本りつ子篇
『コルテス かんばん娘』ガッツ石松+南部虎弾篇
『サッポロ一番 カップ麺』野沢直子篇
『富士通オアシス』出光元篇
『赤城乳業 ラーメンアイス』清水のぼる篇
『赤城乳業 カレーアイス』南利明篇
『タイトー』鳥居かほり篇
『アクティオ AKTIO』稲川淳二篇
『幸せの丘 ありあんす』平尾昌晃篇
『トクホン』吉田日出子篇
『講談社 少年マガジン』花房徹篇
『エステー』斉藤ゆう子篇
『河合塾』デニス・ストック篇
『河合塾』三輪ひとみ篇
ほかに『日清焼そば』『不二家』『ミニストップ』『エバラ焼肉のたれ』『ツカサのウィークリーマンション』『明光商会 MSシュレッダー』『ポッカ レモン100』『飯田のいい家 飯田グループホールディングス』『JTB』『バンダイ BANDAI』『SANARU 佐鳴学院』『講談社 コミック・ボンボン』『母恵夢 ダックワーズ』『ツヴァイzwei』 ──など多数 (制作年は、いずれも1981〜2022のあいだ)
企画のみのCM(ほかのディレクターによる監督演出)は、松下電器(現パナソニック)、松下電工(同)、中外製薬、日立製作所、出光、サンヨー食品サッポロ一番、宝酒造 ──ほか多数
MV
1988『レモン白書』
1988『第一級恋愛罪』
1988『東京ローズ'88』
1988『青いみるく レモンエンジェルのテーマ』
1988『ハンサム・ガール』
(すべて 出演・歌:レモンエンジェル)
ゲーム
1995『バーチャルカメラマン』シリーズ 3DO、LaserActive
1996『螢雪次朗の バーチャフォトスタジオ』 SEGA SATURN
大型映像
1995『あるがままに~The world as it is~』
NHK+NHKエンタープライズ(NHKスタジオパークリニューアル記念特別大型映像)
1998『テーマパークとちぎ健康の森』東北新社
(栃木県立とちぎ健康の森 特別展覧大型映像)
PR映画
1987『高島忠夫の 危機からの脱出』全労済+大広
PRビデオ
1994『山本晋也の トダデナイト』戸田ボート
1996『中村江里子アナが案内する Nestlé』ネスレ日本
ほかにトヨタ、日産、ディズニーランド、シモジマ、西武百貨店 ──など多数
教育セルビデオ
1997『寺田理恵子アナ HACCPの基礎と実際』全三巻 中央法規出版
脚本提供
2000『安藤組外伝 群狼の系譜』細野辰興監督版(共同執筆:星貴則)
製作:レジェンドピクチャーズ